誰かの記憶を辿る
母に誘われて山形県の庄内・最上地方を旅することになりました。

松尾芭蕉の「五月雨をあつめて早し最上川」まさにその季節を感じながら山形を歩きます。


この旅に出発する前に、鶴岡出身の知人に助言を仰ぐことにしました。
何度もLINEでやり取りをしながら、地域のおすすめを聞き、同時にそれらにまつわる個人的なエピソードも伺いました。
初めて行く土地で、以前そこに住んでいたひとの(それも10代の青春時代に)話を聞くことは、想像力がとてつもなく刺激される行為です。
そんなときに大切なのは「住んでいないとしないこと」をきくこと。

暮らすような旅
「旅をするように暮らし、暮らすように旅をする」
これは自身の人生の基本的な方針です。
ここには詳しく書けないけれど、知人のいくつかの「個人的なエピソード」は、実際に旅を進めながら、それらを追体験することとなりました。


旅に出るときに課しているお約束が、当地が舞台の小説を一冊持っていくこと。
(今回は宮本輝著「錦繍」を持参しました)
物語に描かれている風景や空気を実際に、その場所で感じることは、現実と記憶が静かに重なり合うような感覚のあるとても稀有な体験です。
そしてもし、それが“知っている誰かの物語”だったとしたら。そこに自分が登場するのも、案外悪くないのかもしれません。



他人との旅
今回の庄内旅は、母と妹との3人旅でした。
記憶が確かなら3人で旅行するのは、小学生のときに行った伊豆大島以来。
そのとき泊まった宿では、部屋の中に波の音が聞こえていました。
今回の宿でも、夜になると同じように波の音がして、懐かしくなって妹に「あのときも聞こえたよね」なんてきいてみたり。



実のところ、家族だけれど“他人と旅をしている”ような感覚がありました。
それぞれの時間や価値観があって、幼少のころのずっと一緒にいたときとは少し違う感覚です。
でも、過去の記憶や思い出は共有されている。その距離感ごと受け入れながら過ごす旅も、なかなかよいものです。

あと五県ある
こんなふうに3人で旅ができるのは、あと何回あるのだろうか?
これは親の歳を考えると、いつも考えてしまうことです。


帰りの飛行機で、眼下に月山を眺めつつ、この調子で東北地方を制覇しよう!と話し合って、それはとてもいいアイデアだと感じました。
あと五県ある。それまで元気でいましょう。そう言い合っているうちに飛行機は羽田空港に降りました。

その旅が、“知っている誰かの物語”だったとしたら。
記憶と現実が溶け合う、その舞台に自分が立っているのも、やっぱり悪くないのです。

きょうも、そらのいろを思い出せる1日に
使用機材
歩き旅には小さいカメラは正義です。
旅のリンク集
今回の旅で巡ったところ


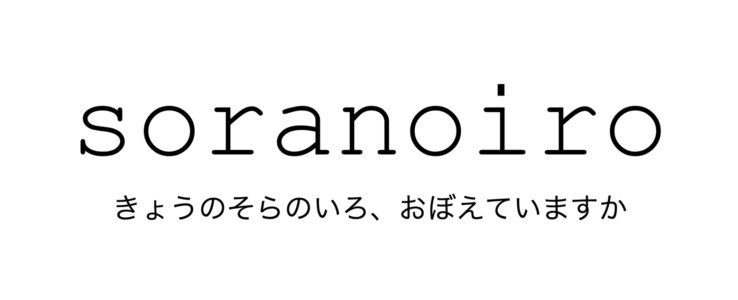



コメント